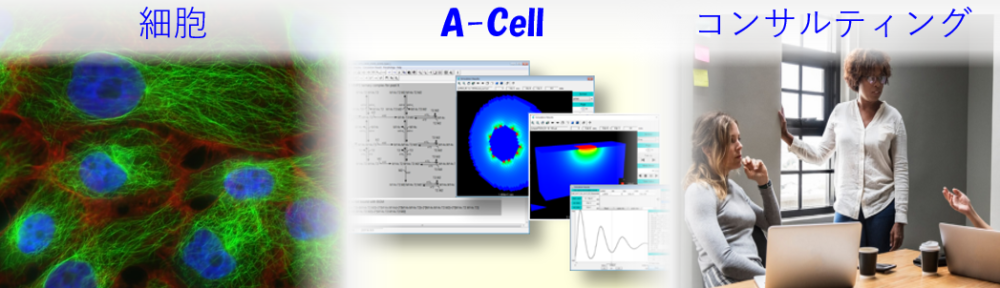(お申込み、お問い合わせはページの下からどうぞ)
細胞シミュレーションは、研究開発を効率化します。
細胞シミュレーションには、実験にはない特徴があります。
細胞シミュレーションでは、すべてのパラメータを変更することができます。これは簡単なことであり、また単純なことです。しかし、この特徴によって研究開発が効率化され、しかも内容を充実させることができます。
例えば、実験で標的タンパク質の活性を制御する場合、inhibitorを使ったりsiRNAを使ったりしますが、手法の習得や実験環境の整備など、多くの手間と時間がかかるうえに、高額な試薬も必要になります。
一方、細胞シミュレーションでは、標的タンパク質の濃度や、KD値、速度定数を変更したり、仮想的inhibitorを導入するだけであり、簡単、短時間、かつ低コストで手間をかけずに実現できます。
さらには、複数の標的タンパク質を修飾してその影響を調べるなど、実験では非常に困難なことや不可能なことを実現することができます。
A-Cellとコンサルティングで、研究開発スピードアップ、手間と予算低減、内容充実へ
弊社は細胞シミュレーションソフトウエアA-Cellをご提供しており、これを用いれば、細胞生物学の知識だけでモデル構築からシミュレーション結果を得ることまで自動的にできます。A-Cell上でパスウェイさえ描けば、シミュレーションの実行まで自動で行うことができます。微分方程式やプログラミングなどの専門的知識は不要です。これによって手間を大きく省くことができ、研究開発が数桁もスピードアップします。
一方、文献や実験データからのモデルの創り方、パラメータの求め方、シミュレーション結果の解釈と解析方法、目標設定の方法など、ノウハウは必要です。弊社は世界的にも最初期(1980年代初頭)から細胞シミュレーションに取り組んでおり、これまでに蓄積したノウハウをコンサルティングを通してご提供します。
これまでに経験した細胞シミュレーション
がんにおける浸潤(MT1-MMPなど)、転写因子と遺伝子発現(NF-κBやERK経路など)、エネルギー代謝、細胞のストレス応答(ストレス顆粒など)、細胞骨格の構造変化と細胞変形(アクチンなど)、骨芽細胞のダイナミクス、神経伝達、網膜視細胞のシグナル伝達、上皮細胞
これらに限らず、ご相談いただいた課題解決に向かって共に歩んでまいります。
コンサルティング開始までの流れ
1) 問合わせ:お問い合わせの後、弊社からご連絡致します。
2) 打合せ:コンサルティング内容、目標、期間等を打合させていただきます。
3) 契約:契約書と秘密保持契約書(必要に応じ)を締結させていただきます。
4) 実施:ご契約に基づいて、コンサルティングを行います。
コンサルティングのお申込み、お問い合わせ
期間、ご予算は内容によって大きく異なりますので、事前にご相談させていただきます。ご相談(無料)だけでも遠慮なくお問い合わせください。